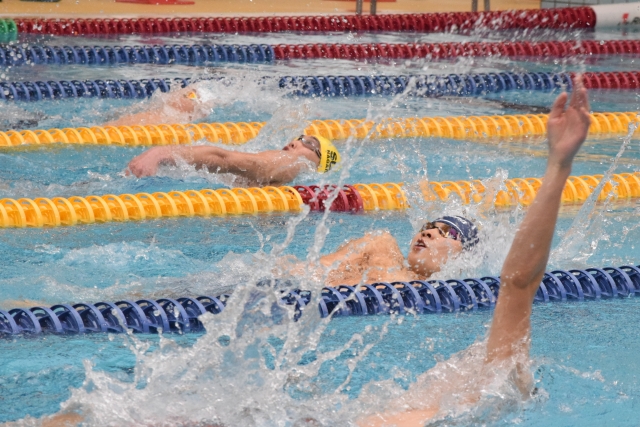まずは自分の現状を言葉と数字で捉え、優先度の高い1〜2点から直していきましょう。
- 入水は肩幅線上で静かに置くように行います
- キャッチは肘を高く保ち前腕で面を作ります
- プルは体幹の回旋でラインに沿って引きます
- プッシュは腿の横まで水を押し切ります
- 呼吸は頭位を崩さずリズムで合わせます
- 道具は課題別に短時間で使い分けます
水泳のプルを速くする基礎|事前準備から実践まで
まずは全体像を描きます。プルは「入水→キャッチ→プル→プッシュ→リカバリー」という5段で構成され、各段に役割が明確にあります。ここを曖昧にすると、余計な力みや蛇行が生まれます。目的は水を後ろへ移動させることではなく、身体を前へ進めることです。水に対する手の軌道だけでなく、体幹の回旋とキックの位相が噛み合って初めて推進が最大化します。
この章では、それぞれの段がどのようにつながり、何を感じ取るべきかを短いキーワードでそろえます。
入水位置は肩の延長線上で音を立てない
手先を遠くへ突き刺すのではなく、肩の延長線上に静かに置く感覚を持ちます。指先→手首→前腕の順に水へ入れると、水面の乱れが少なく後続のキャッチで面が作りやすくなります。入水の深さは手の甲が水面下5〜10cmが目安で、深すぎると肘が落ちやすく、浅すぎると跳ね返りが増えます。
「遠くへではなく、前方の低いドアをくぐる」イメージで肩を詰めないことが大切です。
キャッチは前腕で面を作り肘を高く保つ
キャッチは手のひらだけで取るのではなく、前腕全体で水を捉えます。肘を高く保ち、手先はやや外向きから内へ切り込むと、前腕が板のように水を受けられます。肘が落ちると推進方向に対する有効面積が減り、流れに滑られてしまいます。
小指側から水を感じ、肘を支点に手首を自由に動かす余地を残しましょう。
プル区間は体幹回旋と同調してS字を抑える
引きの区間で手を大きくS字に描く必要はありません。過度な横ブレは抵抗になります。
体幹の回旋に合わせ、肩と股関節をつなぐ線の下を通すように引きます。肩甲骨が前に滑るのではなく、胸郭の回旋で腕を前へ運ぶ意識が、肘の高さと面の向きを保ちます。
プッシュは腿の横で加速を完成させる
水を押し切る終盤は推進の「仕上げ」です。手のひらを後ろへ強く蹴るのではなく、前腕から手のひらまでを一枚のパドルにして腿の横を通しながら後方へ押します。指先は軽く閉じ、最後に手の甲が上を向くと推進が抜けにくくなります。肘が早く伸びきると押す距離が短くなるため、肘角度を徐々に開く時間配分を意識しましょう。
呼吸とリカバリーは頭位を乱さずリズムで管理
呼吸時に頭を持ち上げると骨盤が沈み、プルで稼いだ推進が抵抗に変わります。片眼を水中に残す低い呼吸と、肘の高いリカバリーを同期させると、軸が安定しキャッチが再現しやすくなります。
リカバリーの手は肩甲骨主導で軽く運び、着水直前で力がゼロに近い状態を作ることがコツです。
- 肩の延長線上に静かに入水する
- 前腕で面を作り肘の高さを保つ
- 体幹回旋に同調してまっすぐ引く
- 腿の横で押し切り加速を完成させる
- 低い呼吸で頭位とリズムを守る
注意:肩前面に鋭い痛みがあるときは、無理にハイエルボーを作らず可動域内で面を確保してください。
痛みを我慢して角度だけを追うと炎症を長引かせます。
- ハイエルボー
- キャッチ〜プルで肘を高く保ち前腕で面を作る姿勢。
- キャッチ
- 水を捉える最初の段階。前腕全体で支える。
- プッシュ
- ストローク後半の押し切り区間。加速の仕上げ。
- リカバリー
- 水上で腕を戻す動作。力を抜いて運ぶ。
- 体幹回旋
- 胸郭と骨盤のひねりで推進を助ける動き。
入水とキャッチの精度を上げる具体策

タイムが伸びない多くのケースで、問題は入水の乱れとキャッチの浅さにあります。ここを整えると、同じ力でも前へ進む手応えが変わります。水を「掴む」前に、水を「壊さない」ことを最優先に、手順と感覚のスイッチを用意しましょう。
ドリルは短く、目的を1つに絞るのが成功の近道です。
静かな入水を作る三つの確認ポイント
第一に入水の幅。肩幅線上より外へ広げると軸が蛇行します。第二に入水の深さ。浅すぎると跳ね返りを生み、深すぎると肘が落ちます。第三に手首角度。甲がわずかに下を向くと水面の乱れが抑えられます。
壁を見ながら片手だけでドリルを行い、波紋の少なさを基準にして調整すると早く固まります。
前腕で面を作るための触覚ドリル
プルブイで脚を止め、指先を軽く開いて小指側の感覚を先に立てます。前腕の内側に水圧を感じ始めたら、親指側へ移すように手首を微調整します。この圧の移動が滑らかであるほど、有効面積を保ったまま軌道へ入れます。
手のひらだけに頼らず、前腕全体が「板」になったときの重みを覚えましょう。
キャッチ初動の遅れを解消する呼吸の合わせ方
呼吸をする側の手でキャッチが遅れやすい人は、顔を回す前に軽いキャッチの初動を入れ、顔を戻すタイミングでプルへ移行します。
呼吸で頭が上がると胸も浮き、肘が落ちるので、片眼水中の低い呼吸とセットで練習すると安定します。テンポはメトロノームで一定に保ち、呼吸の有無でピッチ差が出ないかを確認しましょう。
メリット:入水とキャッチが整うと同じストローク数でも進みが増え、疲労感が減ります。水面が乱れずドラフティングも受けやすくなります。
デメリット:序盤は速度が一時的に落ちることがあります。静かさを優先する期間を1〜2週間は確保しましょう。
「手のひらで水を握りしめるほど失速していました。前腕に水圧が乗る感覚へ切り替えたら、肩の力みが抜けて距離が伸びました。」
- 肩幅線上に入水して波紋の小ささをチェック
- 小指側→親指側へ圧の移動を感じ取る
- 呼吸前にキャッチ初動を入れて遅れを防ぐ
- ピッチはメトロノームで一定に保つ
- 片手ドリルは25m以内で集中して行う
ハイエルボーとストローク軌道の最適化
ハイエルボーは目的ではなく手段です。前腕で面を作り軌道を一直線に近づけるために、肘の高さを適切に保つ戦術と理解しましょう。肩の前面を詰めず、胸郭の回旋で手の通り道を作ると、無理のない角度が自然に生まれます。
この章では角度・軌道・力点の関係を数値と表で整理し、ズレを自分で修正する基準を持ちます。
肘角度と推進効率の関係を理解する
キャッチ直後の肘角度はおよそ100〜120度が目安です。角度が小さすぎると肩前面へストレスが偏り、角度が大きすぎると前腕の有効面積が失われます。
体幹回旋のピークに合わせ、角度を徐々に開いていくと、プル区間で速度が落ちにくくなります。動画で静止画を切り出し、角度の変化を可視化しましょう。
軌道は胸の下に引き込み蛇行を抑える
手が外へ膨らみやすい人は、キャッチ直後に軽く内へ切り込み、胸の下でまっすぐ引く意識を持ちましょう。
S字は結果であり目的ではありません。体幹回旋に合わせて軌道がわずかに曲がるのは自然ですが、横移動が大きいほど抵抗が増えます。プル後半で肘を先に伸ばさず、手のひらと前腕を一枚で押し進めます。
肩甲骨の動きとハイエルボーの相性
肩甲骨が外へ滑りすぎると肘が落ちます。
胸郭を回しながら肩甲骨をやや内下方へ引き付けると、上腕の支点が安定して前腕の面が保ちやすくなります。陸上で壁に手をつき、肘を高くしたまま肩甲骨だけを滑らせる練習は、安全に角度の感覚を作れる方法です。
| 局面 | 肘角度 | 前腕の向き | 手の軌道 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 入水直後 | 110±10° | やや外向き | 浅い下向き | 波紋を出さない |
| キャッチ | 100〜120° | 内へ切り込む | 胸下へ | 肘を落とさない |
| プル中盤 | 120〜140° | 進行方向へ | 一直線に近く | 体幹と同調 |
| プッシュ | 150°前後 | 後方へ | 腿横へ抜ける | 押し切る |
| リカバリー | 自由 | — | 水上 | 力を抜く |
- キャッチ角度の誤差±10°以内なら良好
- 外への蛇行幅が10cm超なら修正対象
- プッシュ終盤の手速上昇が+10%が目標
よくある失敗と回避策
肘を「上げる」意識で肩をすくめる:
回避は胸郭の回旋で通り道を確保し、肘は結果的に高い状態を作る。
早い段で肘を伸ばす:
回避は前腕の面を優先し、角度は後半まで温存する。
内への切り込み過多で抵抗増:
回避は切り込みは最小限、胸下でまっすぐ引く。
プルブイとパドルの使い分けと練習設計

道具は課題を大きく誇張し、感覚の学習を早めます。ただし使いすぎると本来の姿勢や負荷配分が崩れます。ここでは目的別にプルブイ・パドル・スノーケルをどう組み合わせるかを整理し、短時間で効果を切り出すメニューを示します。
1本あたりの狙いは一つ、反復は短く、動画で確認するのが黄金律です。
プルブイで軸とキャッチを安定させる
脚を浮かせることで上半身の課題が浮き彫りになります。ブイは大きすぎると過度に浮き、キャッチが浅くなることがあるため、まずは標準サイズから。
25m×6本で「静かな入水」と「前腕の面」を基準に、乱れた本数だけやり直す「減点式」で質を担保します。ブイの位置は太もも寄りに固定すると軸が一直線に保ちやすいです。
パドルは面の向きと押し切りの感覚づくりに
パドルは前腕+手のひらの面を意識化し、終盤の押し切りを誇張します。大きすぎるサイズは肩への負担が大きいので、手のひら一回り大きい程度から開始。
「キャッチで水が逃げる」「プッシュで抜ける」癖のどちらが強いかを確認し、課題に合わせて本数を配分します。途中で素手に戻すと、感覚の転写が促進します。
スノーケルで呼吸の乱れを切り離す
呼吸で軸が乱れる人は、スノーケルで呼吸要素を外してからキャッチとプルに集中します。
スノーケル使用時はリカバリーの肘を高く、入水を静かに保つことを最優先に。25m×8本でビデオ撮影し、波紋の小ささと頭位の安定を確認しましょう。
- プルブイで入水と面づくりを減点式で確認
- パドルで面の向きと押し切りの加速を誇張
- スノーケルで頭位を固定しキャッチを定着
- 素手へ戻し転写を確認してから本数を増やす
- 動画は真横と斜め前の2方向を固定で撮影
- 合計1000m以内で質に集中して切り上げる
- 疲労が残る前に練習を終了して記録する
- 翌日もう一度短く復習し定着を早める
Q1:パドルで肩が痛くなるのはなぜ?
サイズ過大か、肘が落ちて面にねじれが生じています。小型にして、キャッチ角度を優先しましょう。
Q2:プルブイで進まないのはなぜ?
入水で波を立てている可能性が高いです。静かな入水と、前腕に圧が乗る感覚を再確認します。
Q3:道具は毎回使うべき?
課題が明確なときだけ短時間で。素手へ戻す転写が最も重要です。
- 25mの減点式は質を保つ効果大
- パドルは手のひら+一回りが標準
- スノーケルは頭位の安定に有効
- 素手への転写ができたら本数を増やす
- 動画は固定角度で比較しやすく
- 合計距離よりも「良い本数」を重視
レース距離別に変えるプルの配分と戦略
同じ技術でも、50と1500では配分が変わります。ピッチ・ストローク長・押し切り時間の三つを距離別に最適化すると、後半の失速が減り、フィニッシュの伸びが違ってきます。
ここでは距離ごとの基準と、実戦でのチェック方法を示します。
短距離はキャッチを速くしプッシュを鋭く
50〜100ではピッチ優位。入水→キャッチの移行時間を短くし、プッシュ終盤の手速を最大化します。押し切りは鋭く短く、リカバリーは肘高でコンパクトに。
ピッチを上げても波紋が大きくならない範囲がベストで、呼吸回数は最小限に抑えます。
中距離はピッチと長さの均衡を保つ
200〜400はピッチとストローク長のバランスが鍵です。
キャッチの角度を守りつつ、プル中盤での失速を避けるために体幹回旋のタイミングを少し遅らせ、推進の波形を整えます。呼吸は一定のリズムで、頭位の安定を優先しましょう。
長距離は抵抗最小化と再現性を優先
800〜1500では、無駄な上下動と蛇行を最小化します。
押し切りは長く穏やかにし、ピッチは心拍と相談して微調整。波紋の少なさとストローク一定が最大の武器です。ラップごとのストローク数とタイムの相関を取ると、崩れを早期に検出できます。
- 短距離:ピッチ高め押し切り鋭く呼吸少
- 中距離:ピッチ×長さの均衡で波形を整える
- 長距離:抵抗最小と再現性で終盤の落ちを抑える
- いずれも入水の静けさは共通の基盤
- 動画とラップ表で崩れの兆候を可視化
- 練習で距離別ストローク数の基準を持つ
- ドラフティング時は波紋の小ささが武器
- フィニッシュは押し切り延長で伸びを出す
- 距離別にストローク数とラップの関係を測定
- 短距離は呼吸回数の上限を決めて練習
- 中距離は体幹回旋の位相を遅らせる試行
- 長距離は蛇行幅を10cm以内へ抑える
- 動画で入水音と波紋の小ささを評価
注意:距離をまたいで同じピッチを強要しないでください。
心拍・レース展開・水質で最適値はずれます。常に「入水の静けさ」と「前腕の面」を優先しましょう。
肩と体幹の強化でプル効率を底上げする
技術だけでは限界があります。肩の安定・前腕の耐性・体幹の回旋力を高めると、角度と軌道の再現性が劇的に増します。ここではジムと陸上でのメニューを整理し、プール外での投資対効果を高めます。
週2回・30〜40分で十分な成果が狙えます。
肩の安定化:外旋と下制の協調を作る
バンド外旋、Y-T-Wレイズ、デッドバグの組合せで肩甲帯の安定を作ります。外旋は軽負荷で高回数、肩甲骨の下制はゆっくりと可動域いっぱいを使うことがポイントです。
痛みがある日は可動域内でのアイソメトリックに切り替え、翌日の水中練習で角度が保てるかを確認します。
前腕と握り耐性:長く面を保つ筋持久
グリップボールやタオルプルで前腕の持久力を養い、手先の硬直を避けます。
またプッシュ終盤での手速を上げるため、チューブで後方へのプレス動作を繰り返します。肘角度を少しずつ開く感覚を、陸上で練習しておくと水中で再現しやすくなります。
体幹回旋力:下半身と上半身をつなぐ
ロシアンツイスト、ケーブルチョップ、メディシンボールスローで、骨盤と胸郭の位相をコントロールします。
「回してから引く」の順序が守られると、肩だけで水を動かす癖が減り、前腕の面を保ったまま押し切れるようになります。
| 種目 | 目的 | 目安 | 注意 |
|---|---|---|---|
| バンド外旋 | 肩の外旋安定 | 20回×2 | 肘を体側に固定 |
| Y-T-Wレイズ | 肩甲帯活性 | 各12回 | 反動を使わない |
| ケーブルチョップ | 回旋力 | 12回×3 | 骨盤と胸郭の連動 |
| タオルプル | 前腕持久 | 30秒×3 | 肩に力を入れない |
| MBスロー | 加速の表現 | 8回×3 | リズムを大切に |
- 外旋
- 上腕を外へ回す働き。肩の前面を守る。
- 下制
- 肩甲骨を下げる動き。肩のすくみを防ぐ。
- 位相
- 骨盤と胸郭のタイミング関係。
- アイソメトリック
- 動かさずに力を入れる収縮様式。
- 表現速度
- 動作の速さ。プッシュ終盤に重要。
Q1:筋トレで肩が重くなるのが不安です。
高重量よりも可動域とコントロールを優先し、翌日の水中で角度が保てたかを合格基準にします。
Q2:回旋系は目に見えた効果が出にくい?
ピッチ一定でストローク長が伸びるか、動画で蛇行が減ったかを指標にすると変化が分かります。
練習の記録と指標でプルを可視化する
最後は再現性の仕組み化です。言語化と数値化で上達の速度が変わります。毎回の練習で同じ視点を持ち、同じ条件で記録すると、改善の前後関係が読み取れます。
ここでは簡単なテンプレートと基準を提示します。
動画の撮り方とチェック観点
角度を比較するには、真横と斜め前の2方向を固定し、同じ明るさで撮影します。
チェックは①入水の波紋②キャッチの肘高さ③プルの蛇行幅④プッシュ終盤の手速⑤頭位の安定の五つ。毎回同じ順で見ると、主観のブレが減ります。
ラップとストローク数の関係を追う
50ごとのラップとストローク数をセットで記録し、相関を見ます。ピッチ一定でストローク長が伸びていれば前進、どちらも悪化していれば技術の崩れか疲労過多です。
週ごとに平均を取り、距離別の基準値を更新しましょう。
言語化テンプレートで感覚を固定
「入水静か」「前腕で圧」「胸下まっすぐ」「腿横押し切り」「片眼水中呼吸」のように、短いフレーズでメモを残します。
毎回同じ言葉を使うことで、良い日の再現が速くなります。
- 動画は角度固定で同条件撮影
- チェック観点は5つに絞る
- ラップとストローク数はセットで記録
- 距離別の基準値を月1で更新
- 短いフレーズで感覚を固定
ベンチマーク例
- 入水の波紋:小さな円2〜3輪以内
- 蛇行幅:10cm以内
- プッシュ終盤の手速:中盤比+10%
- 呼吸時の頭位変化:1cm以内
- 25m片手ドリル:素泳比−2〜3秒
- 400のストローク数変動:±2以内
まとめ
プルは入水から押し切りまでの連鎖で成立し、どこか一つの乱れが全体の効率を下げます。
水泳のプルを速くするには、静かな入水、前腕で面を作るキャッチ、体幹回旋に同調した一直線のプル、腿横での押し切り、低い呼吸という基盤をまず揃えましょう。道具は課題を誇張し短時間で使い、素手へ転写して初めて価値が生まれます。
距離別の配分と筋力づくりを組み合わせ、動画とラップで再現性を管理すれば、同じ努力で得られる推進が増えていきます。
今日の練習では「入水静か」「前腕で圧」の二つだけに集中し、25m×6本の減点式で質を確かめてください。小さな修正の積み重ねが、あなたのベストを更新する最短ルートになります。